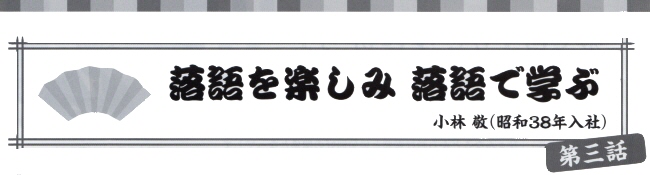 |
|||
|
 |
||
|
上方言葉を早口で喋られたら江戸っ子には聴き取れないということだけでおかしさを構成したのではこの噺の面白さが消えてしまうので、聴き手にセリフの意味を少しずつ感じさせ、印象に残す所がこの噺の勘所である。
この上方言葉が出てくるシーンは、文化的に歴史的に意味のある言葉が数多く登場し、文字に書かれたもので読んでみるとなかなか奥が深い。 「わて中橋の加賀屋佐吉方から参じました。先度仲買の弥一が取り次ぎました道具七品のうち・・・・・」と始まり、この加賀屋佐吉の代理人として来た男は 「弥一が取り次いだという七つの品」について伝言を頼むのだが・・・。 「七品のうち、祐乗・光乗・宗乗三作の三所物、ならびに備前長船の則光、四分一ごしらえ横谷宗珉小柄付きの脇差、あの柄前は旦那はんが古鉄刀木(ふるたがや)と言やはってたが埋もれ木じゃそうにな、木ぃが違ぉとりますさかい、念のためちょっとおことわり申します。次はのんこの茶碗、黄檗山金明竹、寸胴の花活け、『古池や蛙とびこむ水の音』あれは風羅坊正筆の掛物で、沢庵・木庵・隠元禅師貼り交ぜの小屏風、あの屏風はなぁもし、わての旦那の檀那寺が兵庫におまして、この兵庫の坊主の好みまする屏風じゃによって兵庫へやり、兵庫の坊主の屏風にいたしますとなぁ、かようにお言伝け願います」 骨董品を取り扱う道具屋のセリフゆえに専門用語が続き、与太郎でなくても理解に苦しむ。「祐乗・光乗・宗乗」は、刀剣類の装飾金工家後藤祐乗・光乗・宗乗。「三所物」は日本刀の小柄(こづか)・笄(こうがい)・目貫(めぬき)を言う。 この後、日本刀の各部位の名称が登場し、予備知識がないととても理解できない。 「四分一ごしらえ」とは、銀と銅の合金の成分割合を示すもので「銀25%銅75%」のものを言う。「小柄」「脇差」「柄前」と刀に関する専門用語が続き、「古鉄刀木(ふるたがや)」で驚いてしまうが、「鉄刀木」は植物の名前で、「タガヤサン」という熱帯産の植物。つまりこの一節は「刀の柄の部分の素材の説明」をしている。 そして刀の話が終わると次は茶碗の話に移る。「のんこの茶碗」の「のんこ」は陶芸家の楽道入の別名で、正しくは「のんこう」らしい。 「黄檗山金明竹、寸胴の花活け」とは、黄檗山の金明竹(マダケの一種で独特の色と模様がついた竹)を使って作った寸胴の花活けを意味する。 そして、この落語の「落ち」に向かって重要な働きをする一節が「古池や蛙・・・」。 松尾芭蕉(別名:風羅坊)直筆の掛け物というわかりやすい品で強く印象付ける。 以上 |
|||